お知らせNews
防災用品は会社に最低限の義務?備えを徹底解説

企業の防災対策について何から手をつければいいのか、どのような防災グッズを揃えるべきか、あるいは法的な義務があるのかどうかといった疑問をお持ちではないでしょうか。近年は自然災害が頻発しており、従業員の安全確保や事業継続計画(BCP)の観点から、会社における防災対策の重要性が高まっています。しかし、その備蓄品はどこまでが企業の責任範囲なのか、企業向けの災害備蓄ガイドラインにはどんなことが書かれているのか、会社防災義務としてヘルメットも必要かなど、多くの疑問が生じるものです。職場防災備蓄品の目安がわからず、何をどれだけ準備すれば良いか悩むこともあるでしょう。特に、職場防災グッズは女性の視点も考慮する必要があります。これらの疑問に対し、企業が果たすべき防災対策を専門家の知見から解説します。この記事を読めば、会社防災グッズ義務や防災備蓄品企業の目安といった基本的な事柄から、大口の相談はひかりBOSAIへといった具体的なソリューションまで、あなたの不安を解消するための情報が得られます。
企業における防災用品備蓄の最低限の義務とは?
労働契約法に基づく安全配慮義務とは
企業は従業員の安全や健康を守るため、労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」を負っています。これは、企業が従業員の命や身体の安全に配慮し、快適な職場環境を確保するという義務です。災害時には、この安全配慮義務が特に重要になります。例えば、災害によって従業員が怪我をしたり、命の危険にさらされたりする事態を防ぐため、企業はできる限りの対策を講じなければなりません。たとえ自然災害であっても、企業が適切な対策を怠った結果、従業員が被害を被った場合には、この安全配慮義務違反に問われる可能性があります。そのため、企業は災害発生時に従業員が安全に過ごせるよう、防災用品を備蓄しておくことが求められます。
罰則がない努力義務の法的背景

企業が防災用品を備蓄する「会社防災グッズ義務」は、労働契約法で直接的に罰則を伴う形で定められているわけではありません。しかし、多くの自治体では、企業に対して防災用品の備蓄を「努力義務」として位置付けています。例えば東京都では「東京都帰宅困難者対策条例」により、従業員の3日分の食料や水などの備蓄が企業に求められています。努力義務とは、「〜するよう努めなければならない」と規定されているため、違反しても刑事罰や過料といった法的制裁を受けることはありません。しかし、だからといって備蓄を怠ることは、社会的な責任を果たしていないと見なされ、企業の信用を損なうことにもつながりかねません。これは、リスクマネジメントの観点からも無視できないポイントです。
訴訟リスクから見る会社の防災グッズ義務
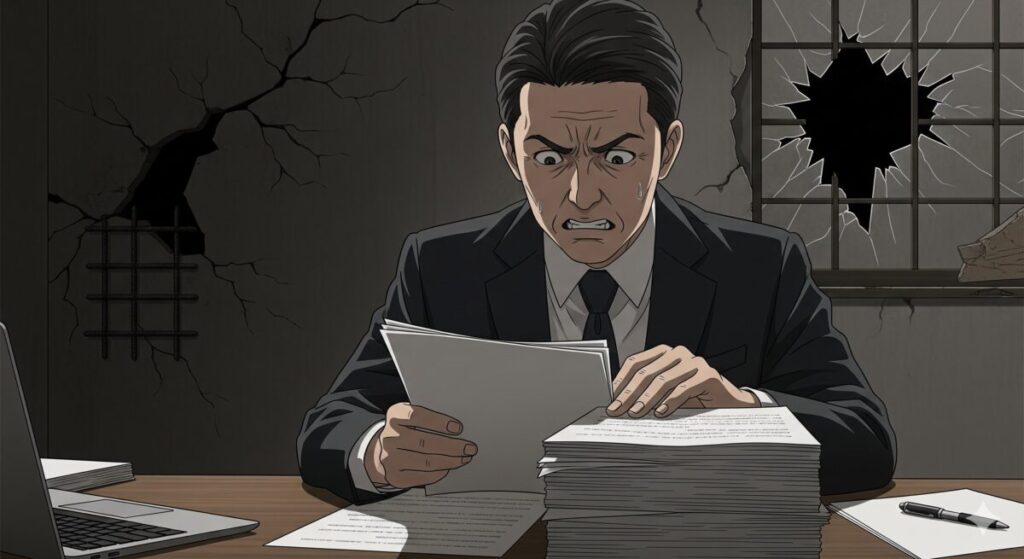
前述の通り、防災備蓄は法律で罰則が定められている直接的な義務ではありません。しかし、もし企業が十分な防災対策をしていなかったことが原因で、災害時に従業員が被害を受けた場合、安全配慮義務違反として法的責任を問われ、損害賠償を請求されるおそれがあります。過去の災害では、対策を怠った企業に対し、数億円から数十億円もの賠償金支払い命令が下されたケースも少なくありません。これらの判例は、企業が従業員に対して負う安全配慮義務が、自然災害発生時も例外ではないということを示唆しています。労働契約法には具体的なペナルティの規定はありませんが、結果的に訴訟や賠償責任につながるリスクは軽視できません。
帰宅困難者対策における企業防災
特に都市部では、大規模災害発生時に交通機関が停止し、多くの帰宅困難者が発生することが想定されます。もし企業が十分な備蓄がないなどの理由で従業員を一斉に帰宅させてしまうと、道路が混雑し、救助活動の妨げになる可能性があります。また、従業員自身も二次災害に巻き込まれるリスクが高まります。このような事態を避けるため、企業が防災備蓄品を備え、災害発生から数日間は従業員をオフィスに留めておくことが、社会的な責任として求められています。これにより、従業員の安全確保はもちろんのこと、都市機能の維持にも貢献することができます。これはBCP(事業継続計画)の一環であり、企業防災の重要な側面です。
職場の災害備蓄品目安とBCP
企業が災害に備える上で、BCP(事業継続計画)は欠かせません。BCPは、災害や事故などの緊急事態が発生した場合でも、事業の損害を最小限に抑え、早期復旧を実現するための計画です。職場の災害備蓄品目安は、このBCPにおいて重要な要素の一つです。災害発生後、電気やガス、水道といったライフラインの復旧には最低でも3日かかるとされています。そのため、従業員が事業所内で安全に過ごせるように、最低でも3日分の備蓄品を準備しておくことが強く推奨されます。具体的には、飲料水、非常食、簡易トイレ、毛布、懐中電灯、医薬品、情報収集ツールなどを用意しておく必要があります。これらの備蓄は、単に備えあれば憂いなしというだけでなく、事業を継続していく上で不可欠な要素です。
在宅勤務でも防災は企業の責任
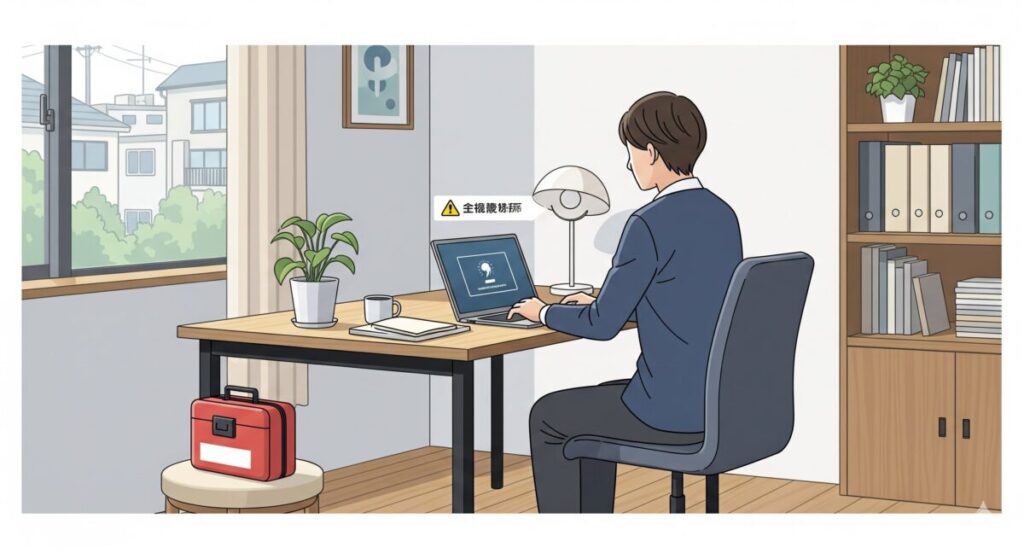
近年、リモートワークや在宅勤務が普及していますが、勤務形態がオフィス勤務でなくても、従業員に対する企業の安全配慮義務が免除されることはありません。自宅で勤務する従業員についても、企業は安全を確保するための対策を講じる必要があります。例えば、福利厚生制度として防災用品の購入費用を支援したり、在宅勤務手当に防災用品購入費を含めるなどの対応が推奨されています。また、出社と在宅勤務が混在している職場では、社内の出社率を基準として防災備蓄の量を検討することが求められます。在宅勤務の従業員が災害に見舞われた場合、企業が安否確認を行う体制を整えておくことも大切です。
会社が備えるべき防災用品の最低限と、義務以上の備え
企業向け防災グッズの選び方

企業向けの防災グッズを選ぶ際には、単にリストにあるものを揃えるだけでなく、業務内容や事業所の立地、勤務形態を考慮してカスタマイズすることが大切です。例えば、製造業のように工場で勤務する従業員が多い会社では、避難や救助に役立つ工具類や、怪我に備えた救急セットを充実させる必要があります。一方で、オフィスワークが中心の会社であれば、情報収集ツールや通信手段の確保がより重要となるでしょう。また、備蓄品の賞味期限や使用期限を定期的に確認し、新しいものと入れ替える「ローリングストック」を導入することも重要です。これにより、常に新鮮な備蓄品を確保することができます。
企業災害備蓄ガイドラインから見る必要な備蓄品
企業災害備蓄ガイドラインでは、従業員が災害発生後3日間施設内に留まることを想定し、必要な備蓄品が定義されています。主に飲料水、非常食、簡易トイレなどの備蓄が推奨されています。これらの備蓄品は、災害時の従業員の命を守るために不可欠なものです。
以下に必要な備蓄品の目安を表でまとめました。
| 品目 | 1人あたりの目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 飲料水 | 1日3リットル、3日分で9リットル | 長期保存可能なものを推奨 |
| 非常食 | 1日3食、3日分で9食分 | 加熱不要なアルファ化米、クラッカーなど |
| 簡易トイレ | 1日5回、3日分で15回分 | 携帯用も含む |
| 衛生用品 | マスク、除菌シート、生理用品など | 従業員の人数に合わせて準備 |
| 毛布 | 1枚 | 防寒対策として必須 |
| 情報ツール | 携帯ラジオ、予備電池、モバイルバッテリー | 乾電池式のものが安心 |
| 救急セット | 応急手当のための医薬品、絆創膏など | 胃腸薬、解熱剤なども備蓄 |
会社に備える防災備蓄品目安

会社に備える防災備蓄品目安は、基本的には従業員数に応じて準備することが大切です。前述のガイドラインにあるように、最低でも従業員が3日間過ごせるだけの物資が必要になります。例えば、従業員が100人いる会社であれば、水は900リットル、非常食は900食分、簡易トイレは1,500回分が目安となります。しかし、これらの目安はあくまで最低限の量です。事業所の立地や周辺環境によっては、1週間分程度の備蓄を検討することも重要です。また、備蓄品は従業員がいつでも使えるように、保管場所を明確にし、定期的に防災訓練を実施して周知しておく必要があります。
会社防災義務としてヘルメットも必須
大規模な地震が発生した場合、建物からの落下物や転倒した什器による怪我のリスクが高まります。そのため、従業員の頭部を保護するためのヘルメットは、会社防災義務として最低限備えておくべき重要なアイテムの一つです。ヘルメットは、避難経路の安全確保や、救助活動を行う際にも役立ちます。ヘルメットの備蓄は、従業員の人数分を揃えるのが基本です。また、ヘルメットだけでなく、懐中電灯や軍手、バールやジャッキといった救助用具も用意しておくことで、災害時に従業員が閉じ込められた場合などに役立ちます。
職場に置くべき防災グッズの女性向け備え

防災グッズを準備する際には、女性従業員の視点も取り入れることが大切です。一般的な防災グッズに加えて、職場に置くべき防災グッズとして、女性特有のニーズに対応した備えをすることで、より多くの従業員が安心して過ごせる環境を整えられます。たとえば、生理用品は災害時の衛生環境を保つ上で非常に重要です。また、ウェットシートや歯ブラシ、下着の替えなども用意しておくと、従業員の精神的な負担を軽減できます。さらに、女性向けの簡易トイレや、体温を保つための毛布やカイロも、季節を問わず備蓄しておくと安心です。
大口の相談はひかりBOSAIへ
ひかりBOSAIのトップページはこちら HIHの大口専用サイト(企業団体様用)はこちら
ひかりBOSAIは、企業の防災備蓄について、どのような商品をどれくらい用意したら良いのか、現在の備蓄に何が足りないのかといった相談に乗ってくれます。サイトに載っていない商品でも、大口の相談はひかりBOSAIへといった専門業者に問い合わせてみることで、ニーズに合わせた防災ソリューションを提案してもらえる場合があります。
会社の防災用品は最低限の義務以上の備えが重要
✅ 災害時に従業員を守り、事業を継続するための重要なリスクマネジメント
✅ 自治体の条例では、従業員の3日分の食料や水などの備蓄が努力義務
✅ 防災備蓄品の目安は、従業員1人あたり最低3日分が基本
✅ 飲料水や非常食に加え、簡易トイレや衛生用品も重要
✅ 企業は、防災マニュアルの作成と訓練の実施も行うべき
✅ 在宅勤務の従業員への防災対策も企業の責任
✅ 防災グッズは、業務内容や立地に合わせてカスタマイズする
✅ 定期的な点検と賞味期限の管理が備蓄品を有効に保つ鍵
✅ ローリングストック法を導入することで効率的な管理が可能
✅ ヘルメットや救助用具も忘れずに備える
✅ 女性従業員のニーズに配慮した備蓄も大切
✅ 専門家に相談することで、自社に最適な備蓄計画を立てられる
✅ ひかりBOSAIのような業者は、サイトにない商品の大口相談にも対応
✅ 最低限の義務以上の備えが、企業の社会的責任と信用につながる
本記事は、株式会社ヒカリネットの編集部が、代表で防災士の後藤秀和による監修のもと執筆しました。
HIHの公式サイト(ひかりBOSAI)のトップページはこちら
HIHのAmazon店(ふくしまの防災HIHヒカリネット)はこちら
HIHのヤフー店(ふくしまの防災HIHヒカリネット)はこちら

人気の防災セット




